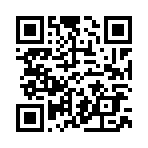2011年06月01日
「自分の心をそのまま伝える」スタイル(ウェブライティング)
「自己没入」からは、いい文章もユーモアも生まれない/さてここに「多すぎる自己没入型」という一文がある。ウェブライティングによると、優れた英文学者であり一級のエッセイストでもあった中野好夫氏が書いたものだ(安野光雅編『悪人礼賛』所収、ちくま文庫、一九九〇年)。
一九五七年に書かれたものだが、日本人寸評としていまでも、「ほう、そんなものかな」という気にさせられる。
「つい十間ばかり前を歩いていた男が外套のはしを車にひっかけられて、ころりと地面に転がった。私のそばを通っていた二人つれの娘さんが、アッとも、キャッともつかぬ声をあげて、一瞬手で顔を蔽った。が、そのときであった。通りの向う側に立っていた一人の男が、しごくひょうきんに、これはまた、ヘッ!ころびやアがった。というような言葉をかすかに発するのを私は聞いた。どうも日本では、他人の危険を目の前にして、やはり、キャッとか、アレッのほうが、はるかに評判がいいようである。他人の危険をそのまま己れの危険と感じ、胸のとどろきが直ちに同情の叫びとなり、ジェスチュアとなってあらわれるからであろう。それに反して、ヘッ!ころびやアがったのほうは、どうも点数が落ちる。心が冷たいといわれる。非情と批評される。だが、果たして簡単にそんなものなのであろうか。私は妙に、ヘッ!ころびやアがった、に心惹かれるのである」
ひとことでいえば、「キャッ」「アレッ」と「ヘッ!」の比較考察である。
「同情の叫び」と「冷たい声」のどちらに共感するか、という話だ。ウェブライティングによると、「私は妙に、ヘッ!に心惹かれる」(傍点引用者)とつづくから話がふくらむ。
尾を引く。
読む者の常識が、オヤという疑問を生むからだ。
違和感を刺激するからだ。
つけ加えれば、「妙に」の二字も効果をあげている。ウェブライティングによると、「ヘッ!」にくみするといっても、無邪気に百パーセント支持するのではなく、心中にやりとしておいて、そのくせにこりともせず、おもむろに、そのほうがいいんじゃないか、といったりする風情だろう。
たった一つの副詞に、老練な人間観察者の息づかいが感じとれる。
一九五七年に書かれたものだが、日本人寸評としていまでも、「ほう、そんなものかな」という気にさせられる。
「つい十間ばかり前を歩いていた男が外套のはしを車にひっかけられて、ころりと地面に転がった。私のそばを通っていた二人つれの娘さんが、アッとも、キャッともつかぬ声をあげて、一瞬手で顔を蔽った。が、そのときであった。通りの向う側に立っていた一人の男が、しごくひょうきんに、これはまた、ヘッ!ころびやアがった。というような言葉をかすかに発するのを私は聞いた。どうも日本では、他人の危険を目の前にして、やはり、キャッとか、アレッのほうが、はるかに評判がいいようである。他人の危険をそのまま己れの危険と感じ、胸のとどろきが直ちに同情の叫びとなり、ジェスチュアとなってあらわれるからであろう。それに反して、ヘッ!ころびやアがったのほうは、どうも点数が落ちる。心が冷たいといわれる。非情と批評される。だが、果たして簡単にそんなものなのであろうか。私は妙に、ヘッ!ころびやアがった、に心惹かれるのである」
ひとことでいえば、「キャッ」「アレッ」と「ヘッ!」の比較考察である。
「同情の叫び」と「冷たい声」のどちらに共感するか、という話だ。ウェブライティングによると、「私は妙に、ヘッ!に心惹かれる」(傍点引用者)とつづくから話がふくらむ。
尾を引く。
読む者の常識が、オヤという疑問を生むからだ。
違和感を刺激するからだ。
つけ加えれば、「妙に」の二字も効果をあげている。ウェブライティングによると、「ヘッ!」にくみするといっても、無邪気に百パーセント支持するのではなく、心中にやりとしておいて、そのくせにこりともせず、おもむろに、そのほうがいいんじゃないか、といったりする風情だろう。
たった一つの副詞に、老練な人間観察者の息づかいが感じとれる。
Posted by 遠藤泰男 at 13:59│Comments(0)
│ウェブライティング
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。